【PR】
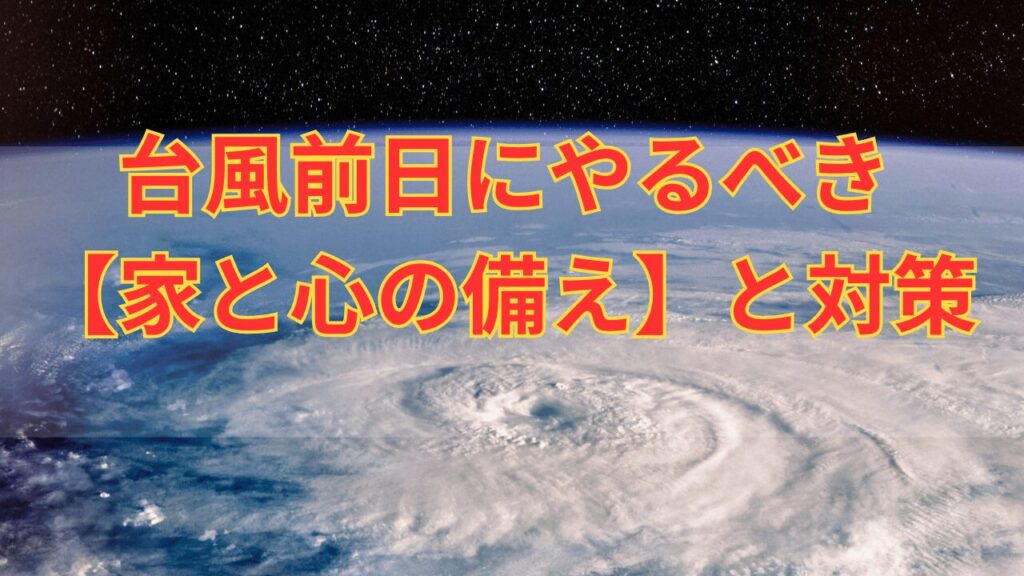
台風前日にやるべき“家と心の備え”と対策についてお話していきます。
~防災士が教える「明日、台風が来る」その日の行動リスト~
台風の進路が発表され、「明日上陸する可能性があります」と言われた時、あなたはどんな行動を取りますか?
「ニュースは見てるけど、まだ様子見かな」
「いつも通り、仕事に行く予定」
「買い物だけ済ませておこう」
…その“油断”が、命を危険にさらすかもしれません。
台風は予測できる災害です。しかし「備えるべきタイミング」を逃せば、何もできないまま暴風域に入ってしまうのです。
この記事では、元消防士で現役防災士の視点から、
「台風前日のうちにやるべき“現実的な備え”」を【家の備え】【心の備え】に分けてご紹介します。
家庭、職場、家族の命を守るのは「あなたの行動」です。
🏠 家の備え|台風の“前日”にやるべき7つのこと
1. 窓ガラスと雨戸の補強
台風で最も怖いのが飛来物によるガラスの破損です。
風圧だけでなく、看板・木の枝・植木鉢などが飛んできて、窓が割れる危険性があります。
✔ 雨戸やシャッターがあるなら、必ず閉めてロック
✔ 雨戸がない窓には飛散防止フィルムや養生テープで補強を
また、厚手のカーテンを閉めるだけでも、ガラスが割れた際の飛散をある程度防げます。
👉 【おすすめ】 窓ガラス用 養生テープ(簡単・剥がしやすい/透明)
👉 【プロ仕様】災害用 飛散防止フィルム90cm×2m(UVカット機能付きで貼ったままでも自然)

2. ベランダ・屋外の“飛びそうなもの”を片付ける
ベランダや玄関先にある以下のようなものは、すべて屋内に取り込むか、しっかりと固定しましょう。
- 物干し竿・ハンガー・布団ばさみ
- 植木鉢・小型の家具
- アウトドア用品・自転車用品
- DIY工具・おもちゃ・ホースなど
👉 【固定用ロープ】アイリスオーヤマ 多目的結束ベルト(2本組)(ベランダ手すりや棚の固定に便利)

※「これは大丈夫かな?」と迷ったものほど飛びやすい傾向があります。
すべて安全側で判断を。
3. 停電・断水に備える(基本セットを前日に完了)
台風が接近すると、停電や断水が起こる可能性が一気に高まります。
前日中に、以下の“最低限セット”を準備しておきましょう。
✅ 充電・ライト・明かり系
- スマホ、モバイルバッテリーのフル充電
- LEDランタン・懐中電灯の点検
- 乾電池(単3・単4)ストック
👉 【高評価】Anker モバイルバッテリー PowerCore 10000(iPhone2回分/軽量)
👉 【停電対策】LEDランタン(防水・3段階調光)(アウトドア兼用・子どもでも使いやすい)

✅ 水・トイレ系
- 飲料水(1人3L × 3日分が基本)
- トイレが使えないことを想定した「簡易トイレ」
👉 【定番】5年保存水 2L×6本(ローリングストックにも最適)
👉 【必携】携帯トイレ 20回分セット(断水時も安心)
4. 食料と日用品の準備と確認
買い足しではなく、「家にあるものの再確認と配置替え」が大切です。
- 非常食・保存食(期限内か?開封しやすいか?)
- 缶詰・インスタント食品(お湯がなくても食べられるか?)
- 調理器具(ガスコンロ or 非加熱食の準備)
👉 【食べやすさ◎】そのまんまOKカレー 5年保存(温め不要)
👉 【まとめセット】非常食 5年保存 7種セット(家族分まとめて備蓄可)

5. 浸水エリアなら「垂直避難」の準備も
低地や海・川の近くなど、浸水リスクの高い地域に住んでいる方は「上の階」への避難も検討しましょう。
- 家族の寝場所を2階に移す
- 大事な書類・通帳・薬などを防水ケースに
- 避難バッグは「すぐ持ち出せる場所」に
👉 【防水◎】ドライバッグ 10L 防災用(浸水時でも安心)

6. 台風対策用の避難グッズは玄関に出しておく
台風の進路次第で、当日突然「避難指示」が出る可能性があります。
- 持ち出しリュックを玄関近くに配置
- 家族全員分の分担と中身の確認
- 避難ルートも合わせて確認する
👉 【定番】防災リュック 30点セット(大人1人用)(必要最低限+軽量)
👉 【子ども向け】こども防災セット(3歳~小学生)(安心の内容と重さ)

7.避難場所とルートを確認
台風や大雨の際、避難が必要になるのは突然です。
そのときに「どこへ逃げればいい?」「どうやって行く?」と迷っていては、避難が遅れ命に関わることもあります。
- 自宅から最寄りの避難所・避難場所を事前に確認しておきましょう。
- 徒歩か車か、どの道を通るか、安全なルートを家族で共有しておくことで、いざという時も落ち着いて動けます。
- 特に夜間や浸水の恐れがある地域では、早めの避難とルートの安全性確認が命を守る行動になります。
👉 ハザードマップや自治体の案内、Googleマップの「混雑レイヤー」なども活用しましょう。
📄 台風に備えるチェックリスト
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓・雨戸は補強したか | 養生テープ/飛散防止フィルム/雨戸ロック |
| ベランダの物は室内に取り込んだか | 物干し竿/鉢植え/DIY用品など |
| モバイルバッテリーとLEDライトは充電済みか | 停電に備えて手元に配置 |
| 飲料水・食料のストックを確認したか | 3日分以上/お湯不要な物も用意 |
| 簡易トイレは用意したか | 断水時に必須/20回分程度 |
| 避難リュックを玄関に置いたか | 中身の再確認/家族全員分 |
| 避難場所とルートを確認したか | 徒歩/車/浸水時の垂直避難も |
💬 台風に備える心|“油断”と“過信”が命取り
台風の怖さは、「いつものこと」と過信してしまう人の行動にあります。
特に以下のような心理は、大きな被害につながりやすいと防災士の立場から感じます。
◆「今まで大丈夫だったから」…本当にそう?
過去に何度も台風が通り過ぎた経験があると、
「また同じように終わるだろう」と思いがちです。
しかし、地球温暖化の影響で台風の強さや進路は年々“異常”化しています。
例:
- 想定外の進路変更で避難所が機能しなかった
- 川が氾濫するはずがないと思っていた地域で浸水被害
- 風でベランダのガラスが吹き飛んだ(過去にはなかった)
👉 今まで平気だった場所も、次も安全とは限らないのです。
◆ 不安を無視しないことが“備え”の第一歩
「自分だけが心配性だと思われたくない」
「避難なんて大げさ…」
そんな声も多く聞きます。
しかし実際には、早めに避難した人ほど「助かった」側にいます。
あなたが行動することで、
家族や地域にも「準備しよう」という連鎖が生まれるのです。
◆ 情報収集は“質”と“正確さ”が命を守る
台風前日~当日にかけて、以下の情報は必ず確認しましょう。
- 気象庁・自治体の発表(防災アプリや公式LINEが◎)
- 避難所の開設情報/避難指示の段階(レベル3~5)
- 自宅が浸水・土砂災害の「警戒区域」に含まれているか
👉 【おすすめアプリ】
情報は非常に大切で、災害時に最も信頼できるものですので、SNSより公式なものから情報を得ましょう。

👨👩👧👦 家族構成・生活スタイル別|備えの工夫
👶 子どもがいるご家庭の場合
- 子どもが安心できるよう「お気に入りのおもちゃ」「絵本」「毛布」を避難袋に
- 水分・ミルク・オムツの備蓄は多めに(3日分以上)
- 避難先での「トイレの不安」「音やにおいのストレス」も考慮
👉 【子連れ避難向け】子ども用防災セット(ぬいぐるみ・ぬりえ付き)

👴 高齢者と暮らす場合
- 階段が使えない状況を想定して1階に一時待機スペースを
- 常備薬・お薬手帳のコピー・保険証の準備
- 補聴器や杖、歩行器の動線確保
👉 【高齢者支援】防災介護キット(ポータブルトイレ・衛生用品付)
🐾 ペットと避難する場合
- 「同行避難」できる避難所かどうかを自治体に確認
- ケージ、リード、トイレシート、水・フードを準備
- ワクチン証明書や写真付き迷子札は必須
👉 【ペット用】同行避難 防災リュック(小型犬・猫対応)
🚶 避難行動の最終確認
◆ 避難指示レベルの意味を理解しておく
災害時、「避難情報が出ていたのに逃げなかった」「そもそもレベルの意味が分からなかった」という声が毎年のように報告されています。
そこでまず大切なのは、「警戒レベルごとの意味」と「自分が取るべき行動」を正しく理解しておくことです。
✅ 警戒レベルとは?
避難情報には「警戒レベル1〜5」の5段階があり、数字が大きいほど危険度が高まります。
しかし、“レベル5が出てから逃げる”では遅いのです。
🔽 警戒レベル一覧と行動目安
| 警戒レベル | 通知内容 | 対象者 | 取るべき行動 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 早期注意情報 | すべての人 | 防災情報の収集を始める |
| レベル2 | 洪水・土砂災害注意報など | すべての人 | ハザードマップの確認・備えの再確認 |
| レベル3 | 高齢者等避難 | 高齢者・要支援者とその家族 | 避難開始。安全なうちに移動する |
| レベル4 | 避難指示(全員避難) | すべての人 | 危険な場所から全員避難。原則“今すぐ避難” |
| レベル5 | 緊急安全確保 | すでに災害発生・切迫 | 命を守る最終手段を取る(屋内での垂直避難など) |
⚠ 注意すべきポイント
- 避難“勧告”は廃止されました(2021年から)
→ 現在は「避難指示」に一本化され、レベル4で全員避難が原則 - レベル5は“避難指示”ではない
→ すでに避難が間に合わない状況で、命を守る行動をその場で取る段階(例:2階に上がる、内側の部屋に移動) - 情報の確認手段は複数持つこと
→ テレビ・ラジオ・防災アプリ・自治体LINEなど
→ 停電時のためにバッテリー式の防災ラジオを備えるのも◎
🧭 なぜ“早めの行動”が命を守るのか?
- 暗くなると避難が危険になる(夜間の水位上昇、視界不良)
- 車での避難は渋滞や冠水で進めない可能性もある
- 自治体によっては、避難所の受け入れ開始が遅れることも
👉 つまり、「様子を見てから逃げよう」は、もはや通用しない時代です。
✅ レベル3=「家族の合図」にする
高齢者がいるご家庭、小さな子どもがいる家庭では、
警戒レベル3を「うちは避難開始の合図」として決めておくのがおすすめです。
- 「レベル3が出たら、おばあちゃんと一緒に避難所へ」
- 「保育園のお迎えはこのタイミングで」
- 「犬をキャリーバッグに入れて車に積む」
→ このように家庭内ルールを事前に決めておくことで、焦らず安全な避難ができます。
✅ 警戒レベルは“命を守るサイン”
- レベル4=全員避難。迷わず行動
- レベル3=高齢者や小さな子のいる家庭は「避難開始」
- レベル5は「間に合わなかった人の最後の行動」=出る前に動くのが原則
「次は自分の町かもしれない」──
そう思って行動できるかが、生死を分けることになります。
どうか、数字の意味を知り、“逃げる力”を家族で持ってください。
👉 「避難」はレベル4で“全員”行う行動です。
◆ 台風当日の動き方:1日のシミュレーション
朝(出勤・通学前)
- 最新の気象情報・警報レベルを確認
- 家の最終点検/外出を控える判断も検討
昼(雨風が強くなる)
- カーテンを閉め、家族で一部屋に集まる
- 停電対策・トイレ準備/防災ラジオで情報収集
夕方(暴風域に入る)
- 避難判断の最終タイミング
- 持ち出しバッグの最終点検/非常食・水を手元に
夜(停電の可能性)
- 懐中電灯は“常時持ち歩く”
- スマホバッテリー温存モードに
- 安全が確認できるまで安静に過ごす
🧠 防災士の本音「こんな備えは意味がなかった…!」
私が現場でよく見かける失敗例をご紹介します。
よかれと思ってやっていたことが、かえって危険を招くケースも多いのです。
❌ 養生テープを十字に貼っただけでは意味がない
台風が近づくと、「窓ガラスの飛散防止に」として多くの家庭で養生テープを十字(バツ印)に貼る光景を見かけます。
しかし実は、それだけではほとんど効果がないどころか、逆に危険が増す可能性もあるのです。
◆ 十字貼りの落とし穴とは?
- 十字に貼っただけでは、ガラス全体の“飛散エネルギー”を抑えられない
- 強風でガラスが割れると、テープが貼られていない部分の破片が鋭利に飛び散る
- テープに引っ張られて、大きく鋭い破片が「まとまって」飛んでくる危険も
つまり、「テープを貼ってあるから安心」と思っていた結果、
割れた破片がかえって遠くまで飛び、けがを招くケースがあるのです。
◆ 正しい養生テープの使い方(最低限の防止策)
- 窓一面を格子状(市松模様)のように貼る
→ ガラス全体を“面”で支えるように - 養生テープ+ダンボール or 厚手のカーテン併用
→ 飛び散りそのものを物理的に遮る効果が上がる - 可能であれば専用の飛散防止フィルムを常設するのがベスト
◆ 防災士としてのおすすめ
👉 【最も安全な方法】
- 飛散防止フィルムを日常から貼っておく(透明で目立たず、紫外線もカット)
👉 【養生テープを使う場合】
- 窓全体を縦横5~10cm間隔で格子状に貼る
- 加えて、室内側に厚手のカーテン or ダンボールを重ねる
👉 【おすすめ商品】
- ニトムズ 窓ガラス用養生テープ(はがしやすく跡が残らない)
- 飛散防止フィルム90×200cm UVカットタイプ
「とりあえず十字に貼っておけば大丈夫」という“安心感だけの備え”は、
災害時には逆に命を危険にさらすことがあります。
正しい貼り方と、補助的な防護(厚手カーテン・段ボール)との組み合わせで、初めて安全性が高まるということを、ぜひこの機会にご家族とも共有してください。
❌ ローソクで明かりをとるのは危険
停電時、「手元にローソクならあるから…」と火を灯してしまう家庭は少なくありません。
しかし、防災士として強くお伝えしたいのは、ローソクは停電時には絶対におすすめできない照明手段だということです。
◆ 停電中の火災発生は“よくある二次災害”
特に、過去の大規模災害では以下のようなローソク火災の事例が報告されています。
- 阪神淡路大震災(1995年)
→ 停電後の暗闇でローソクを使っていた住宅が火元に。復旧中の火災で命を落としたケースも。 - 東日本大震災(2011年)/北海道胆振東部地震(2018年)
→ 停電中にローソクが倒れ、寝具やカーテンに引火する事例が複数
◆ 危険な理由
- 倒れやすい
→ ちょっとした振動・風・ペットや子どもの接触で簡単に倒れる - 近くの物に引火しやすい
→ カーテン、紙、プラスチック、布などが近くにあると火はすぐ広がる - 高齢者・乳幼児の家庭では特にリスクが高い
→ 視覚・反応の遅れ、動作が遅れることで避難や消火が間に合わない - 停電中は火災報知器や消火設備も機能しにくい
→ 火事に気づくのが遅れ、被害が拡大しやすい
◆ 正しい対策は「LEDライト」+「ヘッドライト」+「モバイルバッテリー」
停電時の明かりとして推奨されるのは、以下のような火を使わない照明器具です
- LEDランタン(調光式・吊り下げ可)
→ 安定して明るく、長時間使用可能。子どもにも安全。
- ヘッドライト(両手が使える)
→ 夜間の作業・避難に最適。停電時の“探し物”にも重宝。
- モバイルバッテリー付きのライト
→ 充電と明かりを1台でまかなえる優れもの
「明かりが必要だから」と安易にローソクを使うのは、火災という“別の命の危険”を招く行為です。
とくに、
- 小さなお子さんがいる家庭
- 高齢者や介護が必要な方がいる家庭
- ペットが動き回る室内
では、LEDランタンなどの安全な光源を常備することが必須です。
備えとは「生き延びる確率を1%でも高める」こと。
火を使わない選択は、命を守る一歩です。
❌ 「うちは大丈夫」という思い込みが、命を危険にさらす
台風や豪雨の際に多くの人が言う言葉、それが
「近くの川は今まで氾濫したことがないから大丈夫」
「昔からこのあたりは水に強い」
「避難所まで遠いし、様子見でいいや」
…この“思い込み”が、毎年のように命を奪っています。
◆ 氾濫するのは「想定外の場所」ほど多い
気象庁や国土交通省も警告しているように、
近年は、これまで一度も氾濫しなかった川でも、突発的に溢れる事例が急増しています。
▽ 例:令和元年・台風19号(2019年)
- 東京都・多摩川
→「過去に氾濫した記録がほぼなかった」が、複数箇所で越水・浸水 - 長野県・千曲川
→ 住宅街を含む広範囲で冠水。事前に避難していなかった高齢者の犠牲者多数
👉 「一級河川だから整備されてる」「警報が出てないから安心」と思っていた方の避難が遅れ、多くの被害を出しました。
◆ 川の水位は一気に上がる。“今平気”でも1時間後は危険
特に近年の豪雨は「線状降水帯」などの影響で、
川の水位が“数時間で2〜3メートル上昇”することも珍しくありません。
上流が見えない夜間や、地形が複雑な場所では、
「気づいたときには水が玄関まで来ていた」という声も多く聞かれます。
◆ ハザードマップを「過信」してはいけない
- ハザードマップに載っていない=安全ではない
- 過去の災害データは「過去の平均」であって、「未来の最大」ではない
- 想定外の雨量が降れば、どんな川でも“決壊の可能性”はあります
👉 ハザードマップは「参考情報」であり、「避難判断のすべて」ではありません。
◆ 正しい避難判断のためのチェックポイント
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 警戒レベル4が出ている | 原則“全員避難” |
| 雨が降る前の避難 | 夜間避難が困難なため、明るいうちに行動 |
| 川の近く・低地・旧河川跡に住んでいる | 早めの判断が命を守る |
| 高齢者・乳幼児・ペットがいる | 早め・安全な避難を優先 |
| 車を使うなら時間に余裕を | 渋滞で逃げ遅れるケースも |
✅「命を守るのに、根拠はいらない」
「本当に危ないの?」「避難するほどでもないでしょ?」
そんなふうに感じるときほど、“逃げる勇気”が必要です。
避難して何も起きなければ「無駄足でよかった」と思えばいい。
でも、避難しなかったことで命を落とすリスクは、取り返しがつきません。
✅ 避難の判断は、「川の様子」ではなく「情報と行動」
- 「今まで大丈夫だった」ではなく、「今回は違うかもしれない」
- 「様子を見る」ではなく、「先に逃げる」
- 「念のための避難」が「命を守る行動」になる
どうか、“なんとなくの安心”に流されず、確実な準備と避難を。
あなたの判断が、大切な家族の未来を守ります。

✅ まとめ|「前日」の行動がすべてを分ける
台風は“予測できる災害”です。
つまり、「準備していたかどうか」で明暗が分かれます。
前日にやっておきたい主な準備は以下のとおり:
- 窓やベランダの飛散・破損対策
- 停電・断水に備えた充電・水・トイレ・明かりの準備
- 食料と日用品の確認(お湯不要な食品を含む)
- 家族構成に合わせた避難準備と分担
- 防災リュックと貴重品の玄関配置
- 最新の避難情報の把握と、いざというときの判断力
📄 台風前日チェックリスト(保存版)
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓・雨戸は補強したか | 養生テープ/飛散防止フィルム/雨戸ロック |
| ベランダの物は室内に取り込んだか | 物干し竿/鉢植え/DIY用品など |
| モバイルバッテリーとLEDライトは充電済みか | 停電に備えて手元に配置 |
| 飲料水・食料のストックを確認したか | 3日分以上/お湯不要な物も用意 |
| 簡易トイレは用意したか | 断水時に必須/20回分程度 |
| 避難リュックを玄関に置いたか | 中身の再確認/家族全員分 |
| 避難場所とルートを確認したか | 徒歩/車/浸水時の垂直避難も |
📌 最後に|家族を守れるのは、今日のあなたです
備えをするのは「大げさだから」ではありません。
備えたからこそ“何も起こらずに済んだ”という結果が生まれるのです。
「やっておけばよかった…」と後悔するよりも、
「備えておいて本当によかった」と思える明日にしましょう。

起きてからでは間に合わない。備えとは“命への投資”なんです。
“たった数分”の準備が、命を救います。誰かに任せる時代は終わりました。
自分の命は、自分で守る。家族の命も、あなたの覚悟ひとつで変わるんです。
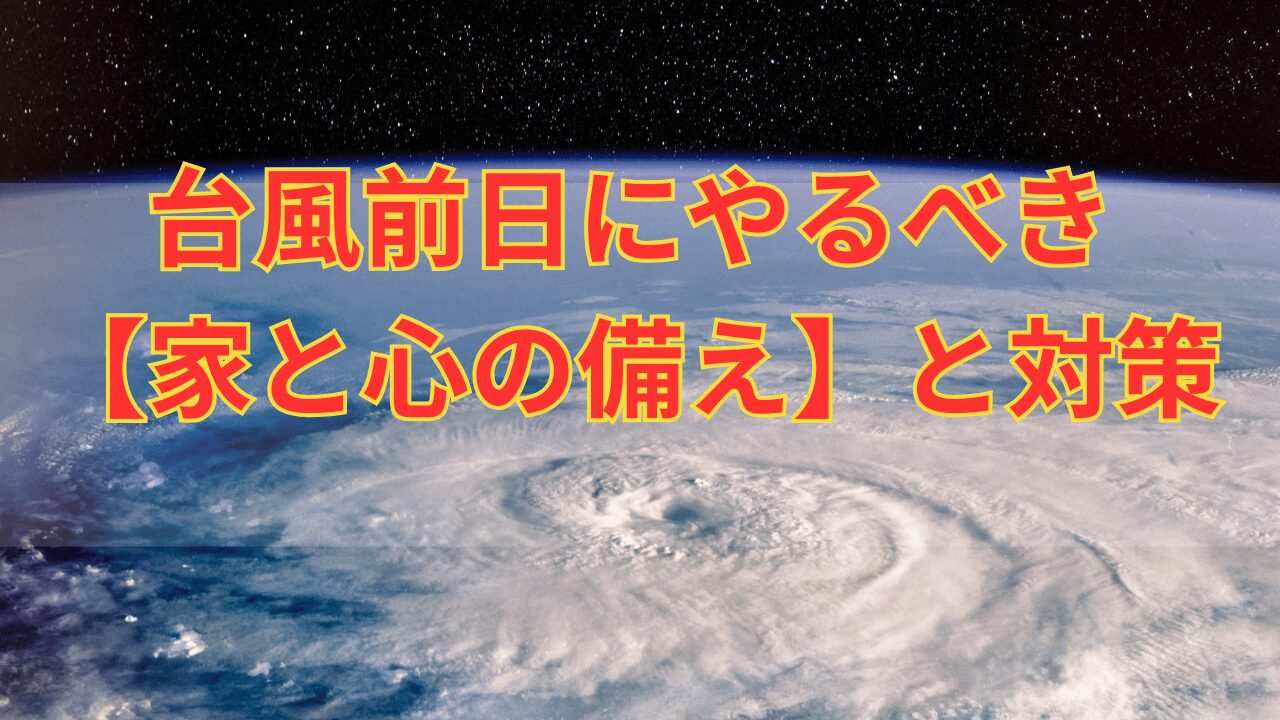






コメント